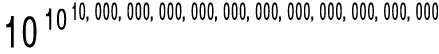『私もあなたと同じ高校に行くわ!」…あの子は、そう言ったんだが…。
あの子は、どこへ?(1) |
| 中学3年の時、高校受験である。 別のところでちょっと書いたが、歩いて行けるところに進学校、自転車で数十分のところに ”そうでもない高校” があった。両方とも県立である。 そして全国的に見れば、どちらもたいした偏差値でもないだろうが、地元では両校には歴然とした格差があった。(当時は偏差値という概念さえなかったけど) ずっと後から実施されるようになった『受験生の強制的な交互振り分け』という仕組みもなかったので、私の家の近所の進学校とされるほうには(今でいう)偏差値が高い生徒が集まり、ますます進学校になるというわけである。 まあ、どうでもいい、くだらないことである。 私は小学生のころから、そういう学歴の表面だけ見る風潮を『奇怪』だと明確に意識していた。 私は田舎の低偏差値の中では、まあ成績は良かったから望む高校に行けたわけだが、 私の明確なの意志として、 「そうでもないほうの高校に行く」 と決めた。 そういう『いちがい(広島弁で、頑固、あまのじゃく)』なことを考えていると、教師や親からしつこく何度も何度も翻意を促された。 担任は怒り、母は泣いた。 しかし、私はそういう【意見】や【情】を気にするタマではなかった。まったく。 まあ、自分で言うのもなんだが、子どもと時から、【まずまず肝いりの変人】だったんである。 さて、ある日の放課後、同級生の一人の女子に進学先を聞かれて、私は上記のようなことを力強く語った。 (言っておくが、彼女はただ単に訊いただけで、私の進学先などに関心はなかったはずだし、私は私のあまのじゃくな意志を彼女が理解してくれるとは思わなかった。それまで誰も理解してくれなかったので) すると驚くべきことに、彼女はこう私に言ったのである。 「●●くん、私もそう思う。私も●●くんと同じ高校に行く!」 なんとも不思議だった。 「こいつは何を言っているんだ?」 最初に言っておくが、彼女は私が好きだから同じ高校に行く、と血迷っているわけではなかった。 私はチョコでなく茗荷タイプなので、一般受けする人間じゃない。 時に怖ろしく『ちょっと普通と違う人が好きな』方々に、すごくマニア受けすることはあるが…。 それはともかく、彼女は恋愛感情皆無で、論理的に私の考えに共鳴した(らしい)。 彼女は医者の娘で医者になろうとしていた(らしい)から、ちゃんとした進学校に行くべきであろう。 なのに、私のあまのじゃくな考えに(全面的に?)賛同すると、力強く宣言したのだ。 どうかしている。 きっと熱でもあったのだろう、 どうかしているが、嬉しくないこともない。いや、嬉しいぞ! 親も担任も(ほほ誰も)理解してくれない私の『変な考え』を支持するというのだから。 「入学式で会いましょう!」 彼女はそう言い、私と握手をした。校舎には夕日が輝いていた。 (・・というふうに、私の記憶ではなっている。美しい記憶だ…) それから、彼女とはその話はしなかったし、話どころかほとんど関りもしなかったと思う。たぶん、そんなに親しくなかったし…。 ともかく、これが私の【記憶。メモリー、思い出…それも美しすぎる思い出】なんである。 そしてそれがいまだに忘れられない思い出になっているのだが、それにはちゃんと理由がある。 そのあと、【そうでもないほうの高校】に私はめでたく、意志通りに入学したが、そこに彼女はいなかった…のだ。 「はて?」 私は、とても不審には思ったが、彼女を責めるような気持ちはまったくなく、 「何か事情でもあったのだろう」 と思った。 事情というより、たんに彼女自身の気が変わったに違いない。 親に泣かれたり、担任に忠告されたのかもしれない。 そもそも一時的にであれ、私の【変な考え】に共鳴することが、もともと奇妙なことなのだ。 賛同者がいようがいまいが、私の信念は揺らぐこともなかったし、新しい高校生活が始まっていたし、バレーボールでオリンピックに行こうとか、ポプコンに出場して、それから自分たちのバンドで将来は東京でプロミュージシャンになろうとか、私は【若き妄想】で忙しかったのだ。 そのうえ、その数か月後には、私のその後の人生を左右するような恋もしたのだし…。 ということで、私は彼女のことは忘れてしまった。 でも、やはりその後もずっとずっと、何かの時に思い出していた。 「彼女は、どこに行ったんだろう?」 って。 【どこ】というのは、【どこの高校】という意味ではなく、(そんなことに興味はなかった)、【どこの価値観】に行ったんだろう?、という意味なんだけど。 そういえば、綺麗でかわいい子だったような…。 |
| (このお題、つづく) |
| <--前 | Home | 一覧 | 次--> |
<スポンサーリンク>